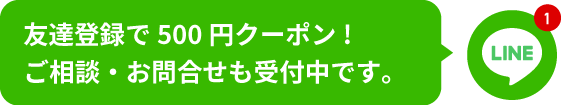「果物は糖質が多くて血糖値を上げるから、食べないほうがいい」と思っていませんか?
たしかに果物には糖質が多く含まれていますが、それ以上に食物繊維やビタミンB群、ビタミンCなど身体に必要となる栄養素も豊富に含まれています。
また、食べる量や食べる時間といった食べ方により、血糖値の急上昇は防げますし、急激な上昇でなければ食後に血糖値が上がるのは正常なことです。
この記事では、血糖値の急激な上昇をさせずに果物を楽しむ方法はもちろん、血糖値とは何かという基本的なことや血糖値が上がることのデメリット、そして果物に含まれる糖質の種類など血糖値と果物について詳しく解説します。
血糖値は気になるけど果物も食べたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
【目次】
- 果物は食べ方次第で血糖値を抑制可能
- 果物に含まれる糖質の種類
- 血糖値が上がることのデメリット
- 血糖値を下げるための食べ方
- 果物は糖質が多いがGIは低い
- 血糖値を下げる成分を多く含む果物
- 果物に含まれる健康にプラスになる成分
- 果物を食べる際の注意点
- 砂糖不使用ドライフルーツでも同じ効果を得られる
- 「カジュベース」は砂糖不使用ドライフルーツ専門店
- 食べ方さえ間違えなければ果物は血糖値を下げられる
果物は食べ方次第で血糖値を抑制可能

果物は糖質が多く含まれる一方、血糖値の急上昇を抑制する食物繊維や血糖値の上昇に直接関係しない果糖が多く含まれています。
そのため、食べる量やいつ食べるかなど、食べ方を誤らなければ、むしろ血糖値の急上昇を防ぎ、さらに健康や美容にもプラスの効果を得ることが可能です。
実際、果物にはビタミンCやB群、そしてミネラルなどの身体に必要とされる成分が多く含まれており、心血管死の約7人に1人は、果物を十分に食べていないことが影響しているという説もあります。
果物に含まれる糖質の種類

果物には糖質が多く含まれていますが、糖質には複数の種類があります。
果物に含まれる糖質で代表的なのは、果糖、ブドウ糖、そしてショ糖です。
血糖値の上昇に深く関わる糖質ですが、それぞれどのような特徴があるのかを確認しておきましょう。
血糖値を直接上昇させない「果糖」
果糖は「フルクトース」とも呼ばれ、その名のとおり果物に多く含まれる糖質です。
果物以外ではハチミツにも多く含まれています。
果糖には以下のような特徴があります。
果糖の特徴
l 血糖値が上がりにくい
l 満腹感を得にくい
l 中性脂肪になりやすい
l 天然の糖の中では最も甘い(ショ糖の1.2~1.5倍の甘さ)
l 冷やすとより甘く感じる
l カロリーはブドウ糖と同じ(1g:4kcal)
l 水に溶けやすい
血糖値とは
血糖値とは血液に含まれるブドウ糖の濃度のことです。
そのため、果糖が直接血糖値を上げることはないのですが、肝臓でブドウ糖に変換されます。
果糖は中性脂肪にもなりやすいので、食べ過ぎには注意が必要です。
果糖は満腹感を得にくい
果糖には満腹感を得にくいという特徴もあります。
果糖を多く含む果物を食べるときには、食べ方に気を付けて、食べる量をコントロールしましょう。
果糖は食べ方次第で健康やダイエットに役立つ
ここまでの説明を読むと、果糖は身体に悪いものに思われるかもしれません。
しかし、果糖には血糖値を上げないというメリットや甘みが強いという特徴があります。
これらを上手く利用し、さらに他の成分と組み合わせることでダイエットや美容、健康にも役立てることが可能です。
生きるために必要なエネルギー「ブドウ糖」
ブドウ糖は「グルコース」とも呼ばれ、果物やハチミツに多く含まれるだけではなく、米や小麦などの穀類、サツマイモやジャガイモなどのイモ類にも多く含まれます。
ブドウ糖を摂取すると血糖値が上がる
そもそも「血糖値」とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。
空腹時で血液100mLに含まれるブドウ糖が70~110mg、食事の2時間後140mg未満なら正常値と言われます。
ブドウ糖を摂取すれば、血液中のブドウ糖の濃度は上がるため、血糖値も上昇するのです。
では、ブドウ糖は身体に悪いものなのかというと、それはまったく違います。
細胞活動の主なエネルギー源となるのがブドウ糖で、特に脳では通常ブドウ糖のみがエネルギーになります。
ブドウ糖は直ぐにエネルギーになる
ブドウ糖は消化を必要とせず、摂取するとそのまま小腸から吸収され、すぐさまエネルギーとなります。
そのため食べて直ぐに満腹感が得られ、食べ過ぎを防ぎやすいというのもメリットです。
その一方で、摂取しすぎると血糖値が急上昇するというデメリットもあります。
果糖とブドウ糖が結合した「ショ糖」
ショ糖は「スクロース」とも呼ばれ、果糖とブドウ糖が1:1の割合で結合した糖です。
砂糖とショ糖の違い
ショ糖は砂糖と同一視されることが多いです。
実は、砂糖の97%以上がショ糖である場合がほとんどで、そのため「砂糖=ショ糖」と考えられます。
ショ糖以外には、還元糖や灰分、水分が砂糖には含まれています。
摂取後のショ糖は果糖とブドウ糖に分解される
ショ糖は食べると、小腸で分解されてブドウ糖と果糖に分かれ、それぞれ吸収されます。
分解される時間が発生するため、ブドウ糖より吸収に時間が必要です。
血糖値が上がることのデメリット

果物に多く含まれる糖の特徴を確認してきましたが、次に血糖値が上昇するとどんな問題が起こるのかを確認しておきましょう。
食事で血糖値が上がるのは正常
気を付けなければならないのは、食事をしたら血糖値が上昇するのは正常です。
【ブドウ糖】の項目で紹介したとおり、ブドウ糖を摂取すれば血糖値は上がります。
そして、ブドウ糖はご飯やパン、麺類など主食に多く含まれているものです。
食後に血糖値が上昇しても、食後2時間たった時点で140mg/dL未満に戻っていれば問題ありません。
問題なのは、血糖値が高い状態が続いてしまうことです。
食後高血糖はさまざまな病気の原因になる
食後2時間以上が過ぎても、血糖値が140mg/dL以上の状態が続くことを「食後高血糖」と言います。
食後高血糖になると、心筋梗塞や肝硬変、そして糖尿病などの疾患を引き起こす恐れがあります。
特に糖尿病は一度かかると簡単には完治できません。
高血糖がさらに長期にわたり持続すると、いくつもの合併症を引き起こします。
血糖値スパイクについて
血糖値について気になる方は、「血糖値スパイク」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
「血糖値スパイク」とは、食事の前後で血糖値が急激に上昇し、その後急激に低下する状態を指します。
血糖値の乱高下の状態をグラフにすると、「トゲ(スパイク)」のように見えるため、この名前が付きました。
血糖値スパイクが身体に及ぼす影響
血糖値スパイクの短期的な影響は、強い眠気やだるさ、集中力の低下といった症状です。
長期的には、血糖値の急激な変動が血管にダメージを与え、動脈硬化を引き起こす恐れがあります。
また、繰り返し血糖値スパイクが起こると、糖尿病のリスクが高まってしまうのです。
他にも血糖値スパイクは、さまざまな体調不良を引き起こす原因となります。
血糖値スパイクは見つけにくい
通常の健康診断では空腹時の血糖値しか検査しないため、血糖値スパイクを見つけるのが難しいです。
そのため、血糖値スパイクの影響が疑われる、食後の強い眠気や疲労感といった症状に注意することが重要になります。
血糖値スパイクが起こる原因
正常な状態なら、ブドウ糖を吸収して血糖値が上昇すると、膵臓からインスリンというホルモンが分泌され、血糖値を適切にコントロールしています。
ところが、インスリンの分泌量が減少したり、分泌のタイミングが遅れたりした場合、血糖値が急激に上昇するのです。
すると、上昇した血糖値を下げるために、大量のインスリンが分泌され、今度は血糖値が急激に低下します。
この血糖値の急激な上昇と低下が、血糖値スパイクの大きな特徴です。
血糖値スパイクは、食べ過ぎや早食い、また空腹状態が長く続いた後の食事でも起こりやすいと言われています。
血糖値を下げるための食べ方

高血糖になると、健康への悪影響が大きいです。
血糖値の急上昇を防ぐためには、どのような食べ方をすれば良いのでしょうか。
血糖値の上昇が穏やかな食べ物を選ぶ
糖を多く含む食べ物でも、血糖値を穏やかに上げるものと、急激に上げるものがあります。
高血糖を避けるためには、血糖値を穏やかに上げるものを選びましょう。
それでは具体的にどのような食べ物が血糖値を穏やかに上げるのでしょうか?
血糖値の上昇が穏やかな食べ物
l アーモンド・クルミなどのナッツ類
l 小松菜・モロヘイヤ・ブロッコリー・オクラ・ほうれん草などの野菜
l わかめ・昆布などの海藻類
l インゲン豆・おたふく豆などの豆類
l 椎茸・ブナシメジなどのキノコ類
l 雑穀米(雑穀の種類によって違いあり)・糖質0g麺などのめん類
l 緑茶
反対に、血糖値が急上昇しやすい食べ物もチェックしておきましょう。
血糖値が急激に上昇する食べ物
l うどん・パスタ・焼きそばなどの麺類
l あんパン・クリームパンなどの甘い菓子パン
l ケーキ・ビスケット・饅頭・羊羹などの菓子
l ジュース・栄養ドリンク・乳酸飲料などの清涼飲料水
組み合わせることで血糖値を下げる食べ物を選ぶ
糖質の摂り過ぎに注意は必要ですが、バランスの良い食事を取ることも重要です。
糖質が多い食品を食べる場合は、食物繊維やタンパク質、ビタミン、ミネラルなどほかの栄養素と組み合わせて食べることで、糖質の吸収を穏やかにすることもできます。
ご飯やパン、麺などは糖質が多い主食よりも、肉や魚、野菜などの副食を多く摂るようにしましょう。
糖質は高めですが、食物繊維やビタミンCを増やすためにデザートに果物を加えるのもおすすめです。
ただし、食事全体での糖質を調整します。
また、塩分や油の摂り過ぎにも注意が必要です。
果物は糖質が多いがGIは低い

血糖値の上昇度合いを表すのに用いられる、「GI」という数値があります。
GIとは、「グライセミック・インデックス(Glycemic Index)」の略で、食後血糖値の上昇度を示す指標のことです。
GIは、血糖値の上昇度合いを、50gのブドウ糖を「100」として相対的に表現します。
オーストラリアのシドニー大学では、GIを3つのランクに分けて定義しています。
l 高GI:GIが70以上の食品
l 中GI:GIが56~69の食品
l 低GI:GIが55以下の食品
果糖はGI値が19、果物は40程度と低GI食品に分類されています。
GIが低い食品は、糖が穏やかに取り込まれ、急激な血糖値の上昇や脂肪をつきやすくする肥満を防いでくれるのです。
ただし、食べ過ぎれば低GIでも、血糖値は急激に上昇する危険があります。
反対に、GIが高くても少量であれば、血糖値の急上昇を避けることも可能です。
GIや含まれる糖質の割合も重要ですが、それよりも大切なのは食べ方です。
血糖値を下げる成分を多く含む果物

果物は糖質が多く含まれているため、血糖値を上げやすいと思われがちです。
しかし、果物には食物繊維やビタミンなど、血糖値の上昇を抑制したり、健康の維持に必要だったりする栄養素が多く含まれています。
そのため、食べる順番や量などに気を付ければ、果物はむしろ血糖値を下げて、健康や美容にプラスになる食べ物と言えるのです。
それでは、血糖値を下げるのにおすすめの果物を紹介します。
リンゴ
皮をむいたリンゴ100gに含まれる糖質は14g程度で、カロリーは53kcalほどと低いです。
また、リンゴには水溶性食物繊維のペクチンが多く含まれており、糖質の吸収を緩やかにして血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。
さらに、疲労を回復するリンゴ酸やクエン酸なども含まれています。
イチゴ
イチゴ100gに含まれる糖質は7g程度で、カロリーは31kcalと低く、血糖値の急上昇を抑えたい方やダイエットをしている方にもおすすめです。
また、イチゴはビタミンCが100g中に60mg程度と豊富です。
キウイフルーツ
キウイフルーツ(緑肉種)100gに含まれる糖質は12g程度で、カロリーは51kcalと果物の中では低めです。
キウイフルーツも血糖値の急上昇を抑えるペクチンが豊富ですし、ビタミンやミネラルなども多く、血糖値対策以外にも、健康を促進する効果が期待できます。
ブルーベリー
ブルーベリー100gに含まれる糖質は10g程度で、カロリーは48kcalほどと果物の中では低いです。
糖尿病のマウスにブルーベリー抽出物を与えたところ、血糖値の低下が確認できた臨床研究があります。
参照:一般社団法人 日本ブルーベリー協会「ブルーベリーのひみつ」
温州みかん
温州みかん100gに含まれる糖質は11g程度で、カロリーは49kcalほどと果物の中では低めです。
温州みかんには、2型糖尿病や脂質異常症の予防効果があるという研究結果が出ています。
さらに、β-クリプトキサンチンという強力な抗酸化作用がある成分が含まれており、生活習慣病予防が期待できます。
参照:農研機構「ミカンとβ-クリプトキサンチン」
バナナ
皮をむいたバナナ100gに含まれる糖質は20g程度と果物の中でも多めですが、カロリーは90kcalほどと意外と低めです。
また、バナナには血糖値の上昇を抑制する食物繊維も豊富であることから、食べ方を間違えなければ血糖値を下げるのに役立ちます。
桃
桃(白肉種)100gに含まれる糖質は11g程度で、カロリーは38kcalほどと果物の中では低めです。
桃は食物繊維が多く含まれ、血糖値の急激な上昇を抑える効果が期待できます。
果物に含まれる健康にプラスになる成分

果物を食事やおやつとして取り入れることは、血糖値を下げるだけでなく、他の健康や美容、ダイエットなどにもプラスになる効果を期待できます。
それでは、果物に多く含まれるどの成分に、どのような効果があるのかを確認してみましょう。
食物繊維
果物の多くは食物繊維を豊富に含んでいます。
食物繊維は、腸内環境を整える手助けをしてくれるので、お通じはもちろん、ダイエットや美容、アンチエイジングへの効果も期待可能です。
また、食物繊維は水溶性か不溶性があり、それぞれ異なる効果を期待できます。
水溶性食物繊維の特徴
水溶性食物繊維はその名の通り水に溶けやすく、水に溶けるとゼリー状になるという特徴があります。
そして、以下のような効果を得られます。
l 小腸で栄養を吸収する速度を緩やかにすることで食後の血糖値急上昇を抑える
l コレステロールを吸着して体外に排出することで血中のコレステロール値を低下させる
l ナトリウムを排出することで高血圧を予防する
他にも、糖尿病、脂質異常症、動脈硬化などの予防も期待できます。
不溶性食物繊維
不溶性食物繊維は水溶性食物繊維とは反対で、水に溶けにくく水分を吸収して便の容積をかさ増しします。
そして以下のような効果を期待できます。
l 便をかさ増しすることで大腸が刺激され排便がしやすくなる
l 有害物質を吸着し便と一緒に体の外に排出するため腸がきれいになる
腸をきれいにすることは、大腸がんのリスクを軽減することにつながります。
また、水溶性と不溶性の食物繊維は共通して、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を改善するという特徴があります。
食物繊維が豊富な果物は、かりん、アボガド、カシスなどがあります。
ビタミンB群
果物にはビタミンB群を含む品種も多いです。
そのなかでも、ビタミンB1、B2、B6が豊富に含まれます。
ビタミンB1
ビタミンB1は、炭水化物などの糖質をエネルギーに変換してくれるビタミンで、疲労回復に役立ちます。
また、脳や神経などに円滑な情報伝達をするためにも必要な栄養素です。
ビタミンB1が豊富な果物には、柑橘類のはるみやきよみ、そしてドリアンなどがあります。
ビタミンB2
ビタミンB2は、皮膚、髪、爪、そして粘膜などの細胞の再生を助けます。
発育促進に必要なビタミンです。
ビタミンB2が豊富な果物は、アボガドやドリアン、レモンなどがあります。
ビタミンB6
ビタミンB6は、多くの酵素の働きを助ける補酵素で、特にタンパク質の分解を助ける働きをします。
他にも、免疫機能の正常な働きの維持、赤血球のヘモグロビン合成、そして肝脂肪の予防効果などが期待できます。
さらに、女性ホルモンであるエストロゲンの合成に加え、つわりが軽減されるという説もあり、女性の味方と言える成分です。
ビタミンB6が豊富な果物は、バナナやアボガド、ドリアンなどがあります。
ビタミンC
ビタミンCは「アスコルビン酸」とも呼ばれ、皮膚や細胞のコラーゲンを合成するために必要な栄養素です。
日焼けを防いだり、免疫機能を維持したりするだけでなく、毛細血管や軟骨などを正常に保つ働きをします。
人間の体内ではなかなか生成できないのも特徴で、柑橘系に多く含まれる成分です。
柑橘系以外の果物では、アセロラやグァバ、キウイフルーツなどに多く含まれます。
ビタミンE
ビタミンEは紫外線から肌を守るメラニンの排出を促します。
強い抗酸化作用もあり、体内の脂質の酸化を防ぎます。
他にも、動脈硬化や血栓の予防、血圧の低下、そして悪玉コレステロールの減少などの多くの効果を期待できます。
ビタミンEを多く含む果物には、うめ、スターフルーツ、ラズベリーなどがあります。
カリウム
カリウムは、体内のナトリウムを体外に排出する働きをするので、高血圧の方におすすめです。
また、長時間の立ち仕事やデスクワークなどによる、ふくらはぎや足首のむくみの解消にも効果が期待できます。
ただし、腎臓の機能が低下している方がカリウムを摂取しすぎると、高カリウム血症になる恐れがあるので注意が必要です。
カリウムを豊富に含む果物は、アボガドやドリアン、メロンなどがあります。
βカロテン
βカロテンは摂取するとビタミンAになり、皮膚や粘膜の健康を維持し、抵抗力を上昇させます。
さらに強い抗酸化作用もあり、老化や動脈硬化、シミやシワの原因となる活性酸素の除去を助けてくれるのです。
βカロテンを豊富に含む果物は、メロンやあんず、パッションフルーツなどがあります。
アントシアニン
アントシアニンはポリフェノールの一種で、眼精疲労の予防や視力・視覚機能の改善などの効果が期待できる成分です。
他にも血液をサラサラにする効果や抗酸化作用、がん予防効果などもあると考えられています。
アントシアニンが豊富に含まれる果物は、イチゴやブルーベリー、カシスなどがあります。
果物を食べる際の注意点
糖質が多い果物ですが、食べ方を間違えなければ、むしろ血糖値を下げる効果を得られます。
では、具体的にどのような点に注意して果物を食べれば良いのでしょうか?
注意点①食べ過ぎないようにする
これは果物に限らず言えることですが、いくら糖質が少ないからと言って食べ過ぎてはいけません。
果糖が多い果物は、食べ過ぎると中性脂肪が増加し、肥満につながります。
注意点②ジュースだと食物繊維が少ない可能性がある
果物は、洗ったり包丁で皮をむいたりする必要があるものが多く、食べるのに手間がかかります。
その点、果汁100%のジュースなら簡単に果物の栄養素をもれなく摂取できる、そう考えたくなります。
しかし、市販のジュースは生の果物に比べ、食物繊維が少なくなる場合が多いです。
具体的にリンゴをサンプルにして比べてみましょう。
|
|
リンゴ(皮なし) |
リンゴストレートジュース |
リンゴ濃縮還元ジュース |
|
食物繊維 |
0.4g |
Tr |
Tr |
|
果糖 |
6.0g |
6.4g |
6.2g |
|
ブドウ糖 |
1.4g |
2.8g |
2.7g |
|
ショ糖 |
4.8g |
1.4g |
1.4g |
※Tr = Trace(トレース)の略で、微量を意味します。成分が含まれているのですが、最小記載量に達していないという意味です。
注意点③薬を服用しているならグレープフルーツは要確認
グレープフルーツには「フラノクマリン類」という成分が含まれています。
フラノクマリン類には、腸管内での薬物の代謝を妨げ、副作用を出やすくしたり、効果を強めたりすると考えられているのです。
そのため、薬を服用している方はグレープフルーツを食べても問題がないか、医師や薬剤師に確認をしましょう。
注意点④食べるタイミング
果物を食べるなら、朝がおすすめです。
果物にある酸味は、筋肉や神経、胃粘膜を刺激して目覚めさせてくれます。
次に食べるタイミングとして良いのは、昼食のデザートやおやつ、そして運動時です。
反対に果物を食べるのを避けたほうが良いのが夜や寝る前で、これはエネルギーを消費しないためです。
注意点⑤1日200gを目安に
農林水産省では、1日に摂取する果物の目標を200gとしています。
ただし、果物は種類によって含まれる栄養素の割合が異なるので、他の食事で足りない栄養素が含まれた果物を選ぶのが理想的です。
それでは、果物200gの目安量を紹介します。
|
温州みかん:2個 |
夏みかん:1個 |
おうとう:40粒 |
|
りんご:1個 |
はっさく:1個 |
すもも:3個 |
|
日本なし:1個 |
いよかん:1個 |
西洋なし:1個 |
|
柿:1個 |
バレンシアオレンジ:2個 |
パインアップル:0.3個 |
|
キウイフルーツ 2個 |
くり:12個 |
びわ:6個 |
|
桃:1個 |
デコポン(不知火):1個 |
バナナ:2本 |
|
ぶどう:1房 |
グレープフルーツ:1個 |
|
出典:農林水産省「果物と健康」
果物は同じ種類でも大きさにばらつきもあります、上記はあくまで目安としてください。
砂糖不使用ドライフルーツでも同じ効果を得られる

200gの果物を毎日食べるのは大変と思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、おすすめしたいのがドライフルーツです。
ドライフルーツは、生の果物に比べるとカロリーも糖質も多くなります。
それは、乾燥させることで栄養が凝縮しているからです。
厚生労働省では、1日のおやつの目安を200kcalとしています。
では、ドライフルーツで200kcalだと、どれくらいの重さになるのでしょうか?
l ドライマンゴー:59g
l ドライアプリコット:68g
l デーツ(なつめやし):71g
l レーズン:62g
l ドライプルーン:95g
l ドライいちじく:74g
l ドライイチゴ:61g
種類によってかなり差がありますが、あくまでおやつとして食べるのなら、少なめにして40~60gがおすすめです。
ドライフルーツなら、皮をむいたり切ったりする必要もなく、かさばりもしないので、小分けにして職場に携帯して食べることもできます。
ドライフルーツはお茶と一緒にたべるのがおすすめ
ドライフルーツを食べる際に一緒にお茶を飲めば、胃の中で水分を吸収して膨らむので、満腹感を得られます。
また、お茶は毎日飲む習慣により、血糖管理が改善され、2型糖尿病のリスクが減り、また糖尿病の進行も抑えられるという調査結果が発表されています。
お茶を毎日飲んでいる人は、まったく飲まない人に比べ、尿中ブドウ糖排泄量が多く、インスリン抵抗性が低下している傾向が示されたそうです。
そのため、ドライフルーツはお茶と組み合わせて、毎日食べることをおすすめします。
ドライフルーツとナッツ類の組み合わせもおすすめ
お茶以外にもドライフルーツと相性が良いのがナッツ類です。
「世界糖尿病会議2013」では、「ナッツ類には糖尿病患者の⾎糖コントロールを改善する効果が⽰された」との発表がありました。
1⽇56g のナッツを摂取したグループの人たちは、空腹時⾎糖が明らかに低下したそうです。
そこで、ドライフルーツとナッツをミックスすることで、血糖値の急激な上昇を抑える効果が期待できます。
ただし、ナッツ類は糖質が低いのですが、脂質は高くカロリーも高めなので、食べ過ぎには注意が必要です。
ナッツ類とダイエットについてはこちらで詳しく紹介しています。
「カジュベース」は砂糖不使用ドライフルーツ専門店

果物の代わりにドライフルーツを食べて、血糖値の急上昇を抑えつつ健康や美容を促進したいという方は、砂糖不使用ドライフルーツ専門店「カジュベース」をぜひお試しください。
ドライフルーツ単品

ドライマンゴーやデーツ、プルーン、レーズンなどのメジャーなドライフルーツから、ドライパイナップル、ドライイチゴ、そしてドライバナナ(バナナチップとは異なります)など珍しいものまで幅広く取りそろえています。
※砂糖は使用していませんが、一部にリンゴ果汁を添加しているドライフルーツがあります。
「ドライフルーツ単品」の購入はこちら
ドライフルーツミックス

カジュベースでは、食べやすい一口サイズにカットしたドライフルーツを複数混ぜ合わせた「ドライフルーツミックス」も豊富に取りそろえています。
組み合わせることで、よりおいしさを増すドライフルーツをお楽しみください。
「ドライフルーツミックス」の購入はこちら
カジュナッツ

「カジュナッツ」はドライフルーツとナッツをミックスしており、血糖値が気になる方に特におすすめです。
カジュナッツは組み合わせが異なる「カジュナッツ01」と「カジュナッツ02」があります。
「【砂糖不使用・無添加・無塩・ノンオイル】カジュナッツ01 300g×2袋」の購入はこちら
「【砂糖不使用・無添加・無塩・ノンオイル】カジュナッツ02 300g×2袋」の購入はこちら
ドライフルーツ小袋

また、カジュベースでは、あらかじめ小袋に入れて小分けにした「ドライフルーツ小袋」も取り扱っています。
「ドライフルーツ小袋」の購入はこちら
食べ方さえ間違えなければ果物は血糖値を下げられる
果物には糖質が多く含まれているものの、それ以上に身体に必要となる成分が豊富に含まれています。
そのため、食べ方を間違えなければ血糖値の急激な上昇を抑え、反対に健康や美容、そしてダイエットなどに有益な効果を得られるのです。
食べる量や食べる時間、そして組み合わせを工夫して、おいしく楽しく血糖値を下げましょう。